Scarlet for me
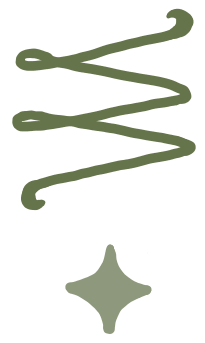
「前々から言おうと思ってたんだけどよ」
そう前置きされた目の前の女はそっと口からビールジョッキを外すと、じっと怪訝な視線をこちらへ向けて静止した。
「錠剤は顎を上げるんじゃなくて、下げて飲むんだよ」ひと口ビールを飲み続ける。「そのほうが飲み込みやすい」
ぱちぱちと何度かまぶたが閉じ開きされた。ごん、と音を立てて宙に浮いていたジョッキがテーブルに下ろされる。
「……なんで、今?」
彼女の小ぶりなくちびるが開くまでにはたっぷりとした間があった。
餃子、小籠包をあてにビールを二杯飲み、油淋鶏、麻婆豆腐、春巻きを追加オーダーし三杯目に手を伸ばしたころである。彼女の言う今、というのは。
昼時は過ぎ、夕食にはまだ早い時間なのでテーブル席で向かい合って座っている俺たちのほかには、カウンター席で競馬中継を見ているおっさんひとりしかいない。
俺の「餃子食いたくね」のひと言でドライブを兼ねて餃子で有名な隣接県まで行く流れになったのだが、車が借りられなかったため、喫煙可ということで大学時代から重宝している近場の中華料理屋で落ち着いていた。それに、どちらかというと餃子が食べたいというより、ビールを飲むために餃子が食べたかったのである。飲んだら乗るな。乗るなら飲むな。これ法律。
「これまでの年月を考えてもなんで今? なんだけど、せめて今日言うなら食事をスタートした時点、わたしがそれを飲んだときではないのかという意味でも、なんで今? と尋ねずにはいられない」
彼女は眉根を寄せてふたたび持ち上げたジョッキに口をつけた。
果たして、数年以上続けられている習慣なんていくつあるんだろうか。
大学の飲みの席でいっしょになったときに、決まって錠剤を飲んでいた女の存在にいつからか気がついていた。プラスチックのピルケースに入れられた、それ。薬をアルコールで流し込むのはほめられたものではないので何度目かのタイミングでなんのために飲んでいるのか尋ねると、なんのことはない、脂肪や糖の吸収を抑える類のサプリメントだった。効果のほどは不明だが、大学で出会って以降数年、体型の露骨な変化を認識したことはないので、あるのかもしれないとは思っている。
「さあ――」誤魔化すようにジョッキに手を伸ばす。「なんでだろうな」
毎度喉に錠剤が詰まっている様子で水もしくは薄い酒を大量に飲んでいる彼女の、そういう喉の違和感みたいなものを俺も今覚えていて、ビールを流し込む。
なんで今なのか。
卓の上にも頭のなかにも、まったく理由の欠片のひとつも見当たらなかった。思いついた瞬間から声に出しているような、アルコールに浮かされている意識もないが。
「てか、ごめん。また仕事の話ばっかになってたわ」
「気晴らしに飲んでんだから気にすんな」
彼女が“また”と言ったのは大袈裟でもなんでもなく、俺はあらかた彼女の職場の登場人物を把握している程度には彼女の仕事の愚痴を会うたびよく聞いている。
昨年中間管理職に昇進した彼女はその責務を全うしているらしい。彼女の話を間に受ければ、彼女はよくやっている。実際、彼女自身も自分はよくやっている、と思っているということは話の端々から伝わってくる。20代半ばでの昇進は早いほうだろうから、それは彼女の有能さを示しているだろう。みんな出世欲がないか自分より要領の悪い人しかいないから消去法なのだ、と謙遜こそすることはあるが。
一歩引いた物の見方のできるやつだった。なによりも器用貧乏でそつがなく、とくになにに対しても一生懸命になれなかったり、とりわけ好きなものがなかったりするのがコンプレックスだと常々言っている。
彼女が働いている姿を間近で見たことはないが、どどどど、とブルドーザーのように仕事をおおまかに軌道に乗せて、溢れたところをあとから拾っていくタイプ。機動力を上の人間には気に入られるのだろう。使い勝手がいいのだ。そして幸いなことに彼女のモチベーションというのはお金や言葉で示される評価で保たれるらしいので、学生時代よりよっぽど今のほうが幸せそうにも見える。
「秘密保持契約でガチガチに固められてて話せることも少ない諏訪くんには申し訳ないですう」
「なんでもかんでも国家機密っつうわけでもねーけどな」
近界民からの三門市への断続的なトリオン兵を用いた攻撃は落ち着きをみせた。三門市へ執拗なアタックや偵察を試みていたおもな国々とはそれなりに平和的な歩み寄りが叶った形だ。
かくして、ボーダーの機能は外務省・自衛隊・防衛省・防衛装備庁に巻き取られることとなった。巻き取られるといっても、ボーダー内にいた人間の成すべきことや働く場に変わりはなかったが、戦闘や防衛以外、つまり人体や生活に活かすためのトリオン研究に関しては省庁が新設され、優秀な人材が集められることになった。
じつに都合のいいことだと思う。日本国民の不安を煽らないためにすべてを三門市の警戒区域内に閉じこめ、時に情報を操作したり改ざんしたりして詳細を明かさず、ひた隠しにしてきたというのに、安全性がある程度担保された途端にこちらへすり寄り華々しく情報を開示し(当然すべてではない)日本にもたらすすばらしいメリットを押し出したのだから。
しかしながら、俺にも都合のいいことはあった。ボーダーという謎の機関の職員ではなく、国家公務員になれることになったわけだ。しかも難関試験は特例免除である。やることは変わらずとも世間体が大幅に変わった。合コンで国家公務員と言えるのはデカいと言える。
「それに、俺は愚痴言うために飲んでるわけじゃねーし、いーんだよ」
わかったようなわかっていないような、聞いているような聞いていないような表情で彼女は麻婆豆腐をすくう。
「そうだ。あれ観た?」
あれってなんだよ、と問う前に、ここ数か月巷を賑わしている映画のタイトルが告げられる。餃子を咀嚼しながら首を横に振れば、彼女はレンゲに口をつける。
「予告とかポスターデザイン的にわたしら向けじゃないなって予感はあったんだけど。付き合いで行ってさ、ツッコミどころ多すぎて疲れた」
肩をすくめると、今度は適温になった春巻きを口に運んだ彼女の言うところの付き合わされた相手というのは男だろうな、という確信に近い勘が働いていた。
「俺もなんか合わねー気はしてたが、おめーが言うならやっぱそうなんだな」
俺は昔から彼女の感性には全幅の信頼を寄せている。彼女が、わたし“ら”と複数人を総称したのは世代などといった巨大な主語などではなく“自分”と“諏訪洸太郎”を指すためだ。まれに、風間やレイジも含まれる。
「そういや、返信したか?」
ん? と首を傾げたのもつかのま、「ああ、うん」こくり、と縦に首が動く。「木崎からわざわざ個別に連絡もあったし、びっくりした。正直、わたしにはお誘い来ないと思ってた」
「それはねーだろ」
先々週あたりにマンションの郵便ポストに仰々しい結婚式の招待状が投函されていた。指先でつまんで表に裏にとひっくり返して見た達筆な住所と名前は、見慣れているはずなのにめずらしい文字の羅列のように思えた。
「だって、諏訪とはこうしてふたりで会うこともあるけどさ、木崎とそれは一度たりともないわけで」
「そら、おめーがレイジと知り合ってからずーっと、レイジには相手がいたわけだしな」
「その間のほとんどの時間、付き合ってはなかったじゃん」
彼女の言うとおり、少なくとも大学生活のすべての時間、レイジはこの度めでたく妻となった女性とお付き合いという形式をとってはいなかった。
「アイツはそういう男だ」
「まあね。風間ともふたりでたまーに会うけどさ。風間は結婚式、呼んでくれるかなあ」
はた、と思わず手が止まる。
彼女は俺を通じて大学一年生のころにレイジと風間と知り合っている。それはたしかなことなのだが、ただ、俺は彼女となんの繋がりで出会ったのかも、あいつらにどういった経緯で紹介することになったのかも、何度か皆で思い出そうとするのだが、だれひとりとして記憶に残っていないのだった。
だからなのか、彼女は俺を介してしか、レイジと風間とは会わないものだとばかり、今の今まで考えていた。だとしても、長年そのことをどちらからも聞かないなんてことがあるのか。たしかに、こないだだれだれに会った、なんて、そう報告し合うことはないか。
「……なんにせよ、レイジはおめーのこと、はなっから頭数に入れてたっぽかったぞ」
「マジか」
「で、出んのか。結婚式」
「ほかにも女性参列者いるって言ってたし、それならって出席で返事したよ」
「ああ」
元玉狛支部の面子――小南や宇佐美栞あたりだろうと察しはついた。
「とりあえず卓は諏訪と風間と同じだって言ってたし。あと、“らいぞーさん”も」
ぴこぴこと両の人差し指と中指が頬の横に添えられエアクォートマークがつく。
「……うっわ、結局会ったことなかったんだっけか」
「そーだよ! 彼、いつも来る来る詐欺だったから」
「そうだったか? そりゃ、変な感じだな」
四人ないしプラスアルファで飲んでるときに雷蔵を召喚しようとしたことが何度かあった。その何度かのうち一度くらいは成功していたものだとばかり思っていた。
「てかさー、木崎ってめっちゃ子煩悩になりそうだよね」とぼやきながら、彼女は店員を呼ぶために片手を上げる。「あ、結婚イコール子どもだなんて、リベラルに綻びが。失礼しました」
彼女が空のジョッキを男性店員に向かって差し出しながら「生」彼女と視線が絡んで「ふたつで」の発声を受け継ぎ、ビールをあおって店員に渡した。
「それはまあ、想像つくんだよなあ」
玉狛にいたキッズの姿を思い出す。すでにある程度の根拠込みで、いい父親になりそうではあった。
「諏訪は子どもってほしいと思うの?」
「あ? まだ結婚すらしてねーしな」
「べつに結婚しなくても子どもはつくれるでしょ」
「そこまでしていらねーよ」ぬるくなった小籠包をかじる。「まー、俺ぁひとりっ子だし、兄弟とかはちょい憧れがねーこともねーかな」
「あ、そっか、諏訪ってひとりっ子か。あんまそんな感じしないよね。面倒見いいし」
ボーダーという年下ばかりの組織に属していれば、後天的に身につけざるを得ない性質のひとつが、それこそ管理職のような側面だった。一部例外があったが、アレらは面倒見を引いてあり余る貢献をしていたから許されたのだ。
「いや、でもあれだ。よくわからんタイミングで人ん家のシャワー浴びはじめたりするし」おしぼりをくるくると丸めながら彼女は言う。「まだみんなデザートのタイミングじゃないのに頼んでたりするし、話盛り上がってるとこでふらっと席外してたり、マイペースなとこあるか」
自分のペース優先というならばおまえも大概だろう、と言いたい気持ちを押し込む。このままこの議論を続けて互いにいい結果が待っているとは思えないのだった。
「おめーはどうなんだよ。子どもは」
「うーん……。わたしの遺伝子が後世に残るのは阻止すべきかなとは思う」 だってさあ、と話は続く。「わたしはわたしが過ごしたかった幼少期を子どもに与えたくなってしまうよ。それに、顔も性格も、わたしに似たらとても生きづらいよ」
お待たせしました、と生中のジョッキがふたつテーブルの端に置かれる。ごん、ごん、と二回鳴った音がやたらと鼓膜にひっついた。
「……今、彼氏いんだっけ」
「今はおりませんけどお。結婚式、ボーダーの人いっぱい来るでしょ? だれか紹介してよ」
片方のジョッキに手をかける指の先の爪がくすんだオレンジ色に塗られているのを見た。
「いい年なんだから、そういうのやめろよ」
えっ、と小さく息を呑むような声がした。
ふたりのあいだに選択ミスや決定的な意見の相違が起こることは、短くはない時間を積み重ねた結果、そうあることではなくなっていた。そういうことを世間一般ではマンネリと呼称するのかもしれなかったし、実家のような安心感、信頼感だと、欲しがるのかもしれなかった。そもそも、出会ったころだって、そんなことはほとんどなかった。
だから、俺はそれこそ「なんで今さらサプリメントの飲み方にアドバイスしてくるのか」と顔を顰めたのに続いて、ほんとうに今日、彼女の戸惑いのような色というものをひさしぶりに感じている。
「……あ、みんな結構年下なんだもんね。そうか、アラサーは無理だよね」
そうだそうだ、とジョッキを持ち上げる。
そうじゃない。そうではないのだ。
「おめーが自分を否定すんのは俺を否定してんのと一緒だぞ」
「え……なんでよ」
――なんでって。
「おめーはもしかしたらほんとうに子どもはいらんと思っとるかもしらんが、未来の旦那が、おまえに似た子がほしいっつったら、まんざらでもねーんだろ」キンキンに冷えたジョッキを掴む。「きみに似る子はしあわせだとか、言ってほしいんだろ」
「ちょっと、なんなの」
「そうやって、自分の価値を他人に委ねんのをやめろっつってんだよ。長年に渡っておめーは唯一無二の存在だと伝えているはずだ」
言ってから冷静にはたと思う。もしかしたら、声に出して伝えてはいなかったかもしれない。それなら、これからは伝えることにしたほうがいいだろう。
彼女はB級と評される映画を観ているときのような、雀荘で灰皿をブン投げはじめた酔っ払いのおっさんを見ていたときのような目をして――それは一体どういった感情なのか、ほんとうに彼女はそのときそんな目をしていたのか――胃袋に勢いよくビールを流し込む俺を見ている。
「――俺にしとけば」
テーブルに置いた中身の液体が減ったジョッキはさっきよりも軽い音を立てた。
「いや、俺にしろ」
なんで、どうして、今日なのか。
タイミングなんざ知ったことではない。長期戦も辞さない構えで煙草の箱に手を伸ばす。
「はいっつうまで、帰さねー」
---> さつきさまより「俺にしとけば」Thank you;) 20250219