ロシアンレッド
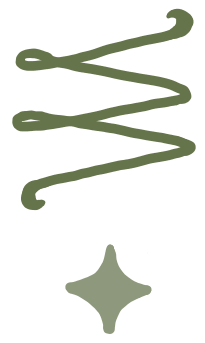
「刺された」
アパートの一階の角部屋。鳴ったチャイムにインターホンを確認せず鍵とチェーンロックを開けた第一声に、わたしは“かまれた”じゃなくて“刺された”派なんだな、と思った。
「刺された」自動音声みたいにくり返す声に背中を向ける。「脇腹」
「じゃあ、はやく閉めてよ」エアコンで冷やされたワンルームの空気と湯気のように湿気た外気が混じり合う。「蚊、入ってくるじゃん。暑いし」
「すまんすまん」
外廊下に立っていた慶の足がドアから外されてガタン、と遠慮のない音を立ててドアが閉まる。
「マジで入っていいの」
おまえは何十回この家に来ているんだ。わたしは今日、おまえが19時に来ると言ったから、それに合わせて帰ってきたのだけれど。この期に及んでなにを言っているのか。
壁にかかっている時計の長針は8を少し過ぎている。文句のひとつでも言ってやろうか、と振り返った。
「――あ」右横腹を押さえている慶の指の隙間からじわじわと滲んでいる、なにか。「……血?」
いやいや、そんなわけ。
去年の誕生日にあげた、左の袖にCのロゴのついた白いTシャツ。血糊を使って汚してまで用意した遅刻に対する渾身の言い訳だろうか。
「人にもらったシャツをそんなにしてまで言い訳しなくてもいいよ」
「ちげーわ。すぐそこでやられた。待ち伏せされてて」
「……なんと」
慶曰く、このアパート近くで何者かに待ち伏せされ、ナイフかなにかで脇腹を刺された、ということらしい。
それこそ蚊を叩いてぴっとついた自分か誰かの血か、月に一度数日間に渡ってやってくる生理かでしか見ないそれに現実味がなかった。生身かトリオン体かはべつとして、それこそ流血よりも“刺す”ことのほうがよっぽど慣れているかもしれない。
わたしは気がつくとポケットからスマートフォンを取り出して、通話履歴の一番上〈太刀川慶〉の下に表示されている〈諏訪洸太郎〉をタップしていた。
「あ――」4コール目で呼び出し音が途切れてざわめきが聞こえた。「諏訪くん」
彼の周りに不特定多数の人がいることはわかるけれど、そこが本部基地なのか大学構内なのか、はたまた違う場所なのか、喧騒からはそこまで判断はつかない。
「慶がね、刺されたって」数分前より確実に広がった朱色を見て、冷蔵庫に貼りつけたタオルホルダーにかけていたスポーツタオルを引ったくって慶に向かって放り投げる。「横腹。右の」慶は俊敏な動き、というよりは反射ですばやく前屈みになってタオルが床に落ちる前にすくい上げた。「血は滴ってはないけど」
『俺じゃなくて119にかけろよ』
「――ああ」
冷静を通り越し頭が冷えすぎて思考停止していたらしい。
一気に身体中に血液がまわりはじめた感覚がして、思わず冷蔵庫にもたれると固い感覚が背中にあたった。慶はわたしが高校時代の部活で使っていた年季の入ったタオルを傷口にあてている。
『出血、そーでもねー感じなら、とりあえず傷口に布当てて異物として認識させて血ぃ止めろ。で、換装させて病院行け』
普通“刺された”なんて現実離れした言葉はボーダー内を除いてニュースの報道以外で聞かないであろうに、諏訪くんはその言葉をそのまま受け取り、疑わなかった。
それはわたしが悪趣味な冗談を言わないと知っているからか、慶が刺されかねないと常々思っているからか。おそらくは、そのどちらもなのだろう。
「うん。そうする」刺された怪我が“そーでもねー”なんてことはあるんだろうか。「ありがと、助かった。じゃあ、また明日」
諏訪くん、犬飼くん、慶、それにわたしの4人で、明日ブースに入ろうという約束をしていた。みな試したいことがそれぞれあって、利害が一致したのだ(慶に関しては、切れれば誰でもよかったのだとは思う)。
だからまた明日、と言ったけれど、この状況では4人で集まるのはむずかしいかもしれない、なんてどうでもよいことを考える。
「血ぃ止まったわ」
「そう……じゃあ、換装したら」
通話の終了したスマートフォンの液晶を見下げたまま提案する。
「――ああ」慶が血で汚れていないほうの手をポケットに突っ込む。「なるほど」一瞬のうちに、この時期に見るには暑苦しくてたまらないコート姿が投影されて血液は見えなくなった。「さすがは諏訪さんだな」
慶はそう言って玄関と廊下の低い段差に腰を下ろした。
ブースや遠征先でトリオン体を刺されるのと、大学から女の家へ向かう道すがらで生身をひと突きされるのとでは勝手が違う。
それは当然の意識だと思うけれど、あの慶ですらも〈換装する〉という単純な対処法に気がつかないということは、彼にも日常と戦闘の境界線がまだどこかにかろうじてあるんだな、とじんわり驚いていた。
「病院行って。タクシーで」
漫画やドラマで見た刺し傷とくらべれば、まったくたいした出血量ではないと思う。切り傷くらいなもので、諏訪くんが言うところの“そーでもねー”であろうという素人判断だ。慶が抵抗したのか、かわしたのか、あるいは刺した側に躊躇いがあったのか、パワーが足りなかったのか。
「行くしかねーかあ」ぽりぽりと顎を人差し指でかく。「世話んなってる先生らに申し訳が立たねーな」
なんとなく予想はしていたけれど、自分に非のあることで引き起こされた事件だという自覚があるのだろう。
配車アプリを起動して、総合病院を目的地に設定すると幸運なことにすぐにタクシーが捕まった。到着は3分後だ。
リアルタイムでタクシーの現在地を表示してくれる地図上で、大通りを走っていたタクシーが不自然に方向転換するのを追いかける。
「おまえとはいつでも戦いたいけど、喧嘩したいわけじゃない」
「……べつに、喧嘩してないけど」
「今、怒ってんだろ」
「心配してるんだけど」
「うそつけ」
わたしにもちったあ申し訳なく思えや。
慶がプライベートで起こすトラブルなんて、女関係に決まっている。
ボロボロと単位を落とすことも面倒ごとではあるけれど、そんなことでは刺されることはない。否、こちらは刺したいくらいに腹が立つことはあるけれど、実際に刺すことはない、というのが正確な言い方だ。
「タクシー来るから、行って。あと2分」
かくかくと鈍い動きのタクシーが右折し、わたしのアパートの前の路地に入った。
「着いてきてくんねーの」
なんでわたしが。馬鹿馬鹿しい。
日々ボーダーと連携して三門市の平和のため、ありとあらゆる活動を行っている先生たちに〈痴情のもつれで刺されました〉なんて、絶対にわたしは説明したくない。へらへら笑っているバカ男の横にもいたくない。
背を向けようとしたところで、スマートフォンを握ったままおろしていた腕を掴まれた。咄嗟のことに両脚の踏ん張りはきかず、情けなく腕を引かれるままにつんのめる。
抱きとめられて溶けるように伝わる、冷房の効きすぎた部屋に心地よい慶の温度はにせものだ。
「待機時間長くなると追加料金とられるんだから、早くして」
「へーへー」
長い腕から解放されて、わたしは今度こそ短い廊下を5歩で歩ききって部屋に足を踏み入れる。壁のスイッチを手のひらで叩き、テーブルの上に置いていたリモコンのボタンを人差し指で必要以上に強く押し込んだ。
---> 辻子さまより「おまえとはいつでも戦いたいけど、喧嘩したいわけじゃない」Thank you;) 20240915