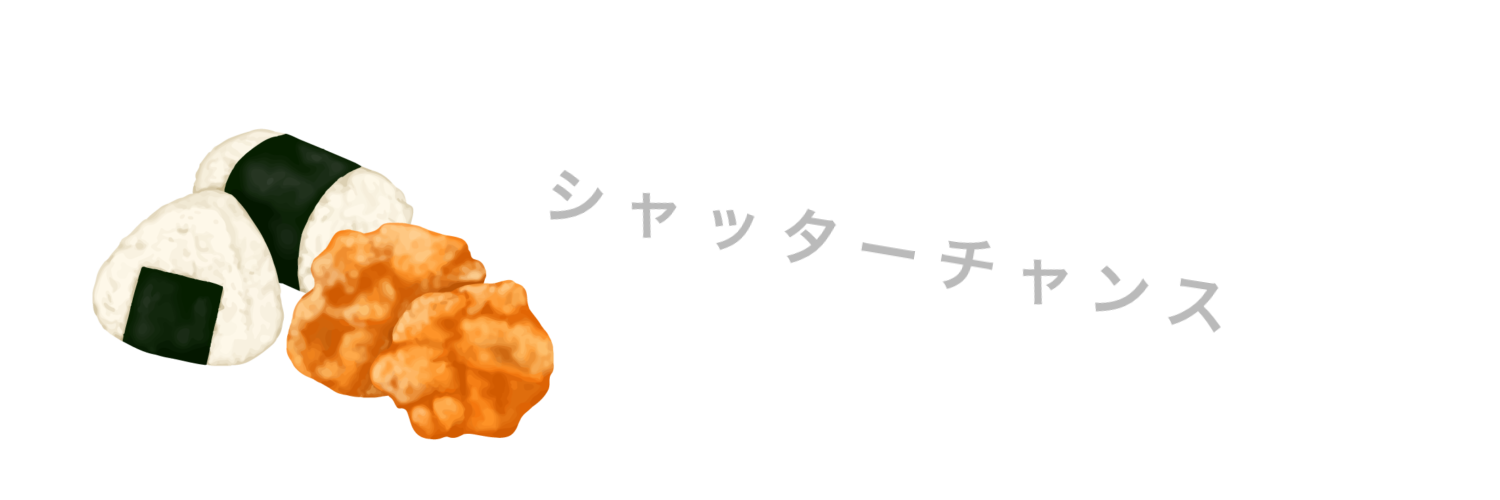
[おにぎり食いにこい]。たった9文字のメッセージが、治からの数年ぶりの連絡だった。
近況を尋ねる導入とかないんか? 手紙の書き出しやったらもうちょいていねいな文章を連ねるやろ? スタンプひとつおされるよりはマシやったか。いや、そのほうが返信について考える必要もなくスルーできたし、よっぽどよかったかもしらへん。
宮治とわたしの関係をかんたんに説明するとすれば、同じ高校に通っていた同級生、ってところだろうか。それ以上でも以下でもない。簡潔に述べずともそれだ。
さしてなかよくなかったのになぜ治呼びかって、そりゃ侑との区別が宮くんではつかないからだ。なぜ連絡先がわかるのかといえば、体育祭の委員会の関係で交換せざるを得なかったと記憶している。
ちなみに、治は侑と違ってそれなりにちゃんと働いてくれた。なんならわたしのヘマもじつはこっそりフォローしてくれたというのを先生から聞いて、お礼がてら朝練終わりの治にからあげクンを渡したことがあった。「半分こしよや」と提案され、わたしは朝ごはんを食べたばかりでちっともお腹はすいていなかったのに2個ずつそれぞれ食べ、5個入りのそれの遠慮の塊を押し付けあっていたら、いつのまにか割り込んできた侑に食べられた。
そんなエピソードは蛇足程度にあるとはいえ、それからとくに仲が深まるということもなく、ふつうに高校を卒業した。以来ばったり出会うということもなく、連絡もしてなかったし、だから開いたメッセージに後悔した。うっかり既読にしなければよかった、と。
それでも仕事終わりにそのおにぎり屋の前まで足を運んでしまった理由は、自分でもよくわからない。うわさで聞いていたその店が現場からここまで電車で二駅と近かったからだろうか。それとも、夕ご飯を求めたか。
“おにぎり宮”の外観・内装は、商店街のお肉屋さんみたいだと思った。小さな店舗にショーケースだけ、食べる場所もない。こじんまりとしていた。ほんなら食いにこい、やなくて買いにこいやろ。筒抜けの店内を立ち止まって外からみていれば、レジの前に立っていた治と視線が交わる。
「来るなら連絡せえや。既読スルーの趣味悪女」
そこまで言われる筋合いはないだろう、と口をとがらせ、一歩二歩とおにぎりが陳列されているケースの前に歩み寄る。商品はもうほとんど残っていなくて、閉店間際だと思われた。
「カメラマンってクソブラックていうし、死んだ顔を拝まなあかんかと思っとったけど」
元気そうでなによりや、と笑顔でつらつらと暴言かほめ言葉かを並べ立てる治におもいっきりしかめっ面を向ける。なんだかとつぜん肩にかけていたカメラバッグの重量が増えたような気がした。なるほど、こいつはどこかのだれかにわたしの仕事を聞いとったんやな。仕事の話がしたいんやったら、はじめからそう言っといてくれや。余計なことを考えさせられた時間を返してほしいわ。
「もう閉めるし、ちょい待っとき」
そう言い残して治は奥に引っ込んだ。手持ち無沙汰になったわたしはバッグのチャックを引っ張り一眼レフを取り出して、中腰で目の前のおにぎりを撮ってみる。こんな撮影のしかたではろくなものにならないので、ほんとうにただのひまつぶしだった。
ふと背後に気配を感じて振り向きながら立ち上がれば、ふくよかなおばさんがわたしににこり、とほほえみかける。お客さんか。奥に向かって来客を叫ぶ。
「撮影?」
女性がわたしに楽しそうに尋ねるのでそんなところです、とことばを濁せば、「もしかしてサムちゃんの彼女さん?」
彼女はおろか、友人と言えるかどうかすらあやしいねんけど。めっちゃ距離感近い感じであちらは接してくるけども。
ちゃいます、と口が動く前に、治はこの女性に常日頃から自分の彼女についてなど世間話をしているのかという想像が働いた。近寄りがたいようで、人なつっこい治。きっとこのあたりの人たちと良好な交流をしているのだろう。
「あら、奥さまやった?」
否定も肯定もないことを、より親密な関係であると発想したか、女性は遠慮のない目線をわたしにくれる。
「ち……」
「おっ、毎度どうもー!」
わたしの否定の声を治のはじけるような挨拶がかき消す。女性の興味は治とおにぎりにうつったようで、わたしはじりじり後退して、外に出た。
わたしの予想はただしく、にこやかに会話を続ける彼らはなんとなく、生きたことがないので映画などで描かれるそれしか知らないが、昭和の下町が似合う。ガラス越しに点在しているおにぎりすべてに人差し指をさす女性は、ぜんぶ購入する気なのだろう。思わず構えたカメラのシャッターをなんどか切った。
手を振るおばさまを治と並んで見送り、これじゃほんまに奥さまみたいやんけ。とひとり心の中でつっこみを入れ、促されるままに裏口から店舗に入った。小さなテーブルとパイプ椅子が3つ、冷蔵庫とテレビが置いてある小さな休憩室だった。
テーブルの上には木のプレートに載せられたおにぎりがふたつ待っていて、こちらお食べくださいということらしい。治がポットを押して急須にお湯を入れている。
「ほら、これじゃあかんやろ? 湯気とかなんやら、ちゃんとつくるからうまそうにみえんねん」
急須と湯呑みをふたつ運んできたばかりの治に、カメラの小さな液晶のほうを向けて突き出す。
たとえばビールの撮影にはシズル師という、水滴や泡、それだけをつくるためのプロがいる。アイスをすくうスクープのあとをきれいにつけるのは意外と難易度の高いことで、それが唯一できる社内の人間がそれだけを武器に出世したという伝説もある。撮影にはなにも機材だけあればよいということではないのだ。
「せやから、駆け出しのわたしに依頼したとてそれなりのもん撮るにはそれなりにかかるで」
そう説明すれば、湯呑みに緑茶を流し込みながら、治はなるほどなとひとつうなずいた。ほんまにわかっとんやろか。やんわりとわたしが手伝いを拒否しているということを。
「今のうちから代理店かませて、長期的に考えたほうがええんちゃうん?」
治のことだ、この規模で終わらす気など毛頭ないに決まっている。押しやられた湯気のたつ湯呑みにふれれば、わかってはいたことだが熱くてまだ口にする気にはなれなかった。
「まあな」
「紹介しよか?」
「なんや、知り合いにおるんか」
「わたしが働いとるとこやけど」
「カメラマン1本でやっとるわけやないんか」
テーブルに放置されていた一眼レフを断りもなしに治は自分のもとに寄せる。どうやら十字ボタンでわたしが撮影した写真をながめているようだった。
専門学校を卒業したあと、カメラマンのアシスタントについてもよかったのだが、わたしはレンズ越しにたくさんのものをみるより、外からものを見る時間がほしくて広告代理店で営業アシスタントをすることにしたのだった。だから治の言うとおり、カメラマンという職業だけで生計をたてているわけではない。
「そうそうカメラじゃ食べてかれへんよ」
「食べられとるやん」
「え?」
まだカメラをいじって顔をあげない治にまぬけな声をあげれば、視線はそのまま、片腕がのびてわたしの目の前に並んでいるおにぎりを指差した。はっきりと口頭ですすめられたわけではなかったので、まだきれいなかたちでそこにいた。
「俺とお客さんが会話してるこの写真、めっちゃええ」
突き返された画面は蛍光灯が反射してよくみえはしなかったが、ついさっき、わたしが撮影したおばさんと治の写真のことだろう。
「これ1枚、おにぎり代差し引いた価格で買うで」
「えっ」
「不満か?」
「……いや」
不満なわけがなかった。頬がほてるのはなにも顔をつつむたちのぼる湯気のせいだけではない。むしろ、踊り出しそうなほどうれしくて、そのにじむ興奮をおさえることに必死だった。
とはいえ、その写真がいいのはわたしの腕がどうとかではなく、治の人格があってこそのものだろう。それでも、その光景を切り取ることができたのはわたしがいたからだ、とはさすがに思う。
「カメラ1本で食ってくことは、が現時点で求めてないんやろ」
治の否定待ちではないほとんど断言に近い考察にたいしてしずかにうなずけば、「俺はのそれが逃げとは思わへんし、べつに1本やなくてがっかりしたわけちゃうで」
わざわざフォローまで入れてもらっちゃあ、わたしもあいまいに笑みをつくるしかない。やっぱり治は、高校時代から変わらず、そういうやつなのだ。
「高校んときみたいに、しあわせそうに見えるしな」
「なにそれ」
「いつもたのしそうにしてたやん」
「いつもって……」
どういうこと? 問いただすことばを吐こうとしたけれど、考え直しておにぎりを持ち上げる。
聞いて、確認して、なにをどうするつもりだろうか。なにがどうなるのだろうか。ますます上昇してゆく体温の理由は不自然にはやまった心臓の動きでわからないこともない。
「ま、その話は追々として、代理店紹介してくれ。ただしカメラマンは専属な」
「はあ……」
いろんなことをごまかすように、わたしはひとくちおにぎりにかぶりついた。もうあたたかくはないはずなのに、ほくほくとする温度があるようだった。お腹がすいていたことを、脳みそが思い出す。
「あと、すぐにでも安心安全の生産者北さんの写真も撮り行くで」
「…………えっ、北さんて、あの主将の北さん?」
咀嚼途中のおどろきの発言にいそいで飲み込んで確認する。自分のことのようにほこらしげな治の顔をみれば答えを聞かずとも同一人物であることは理解できたが、せやで、と治が肯定した。
「そりゃ信頼のお米、うまいわけや」
「俺のこともほめろや」
「……おいしいよ。ほんまに」
食べもんをつくって売っとる人間に、おいしい。最高のほめことばやろ? それなのになぜだか不満そうな治の顔をながめながら、もうひとくち頬張った。北さんのことはよう知らんけど、顔のわかる人がつくったお米だとわかればなおのことうまいような気もしてくるから、ふしぎや。
「……まぁ、まずいおにぎりとか食べたことないけどな」
「おまえなぁ」
治がそう言うのならば、あれもこれも、問いつめる機会はまたすぐにでもあるのだ。それは同時に、わたしにもそうされる機会があるとも言えるわけやけど。
お米食べたら、からあげ食べたくなってきたわ。──そうつぶやけば、ゆるく弧をえがくような治のくちもとに、わたしは逃げ出したくも、笑い出したくもなった。