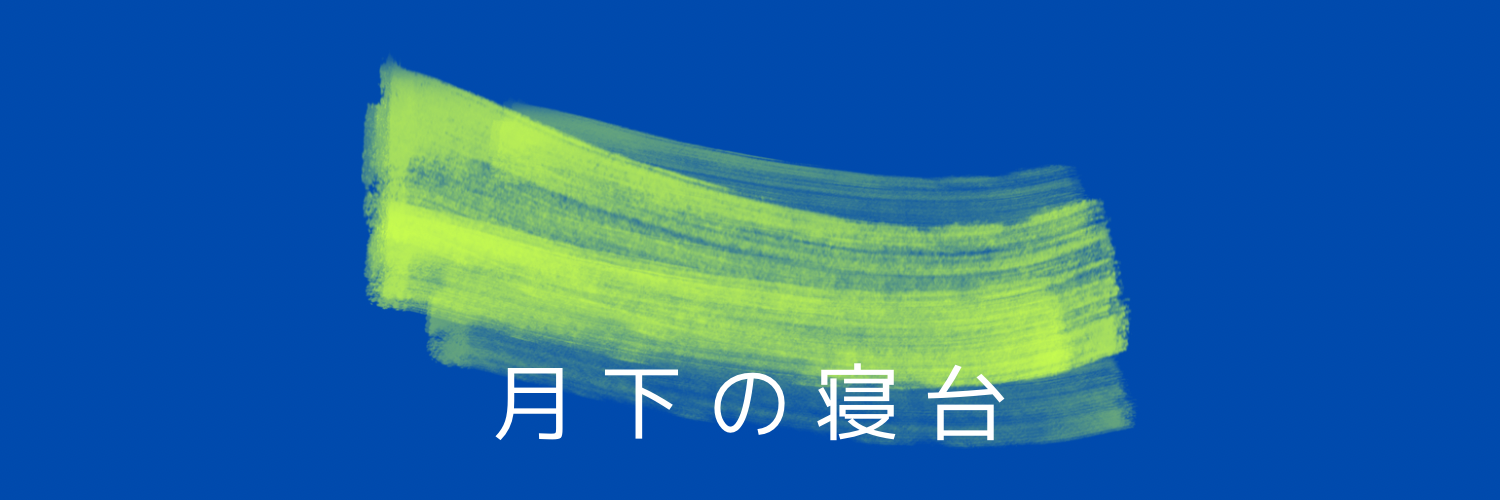
祖母が亡くなったのはほんとうに突然のことだった。
年齢なりに持病はあったけど、ほとんど毎朝わたしのお弁当をつくってくれていたし、庭いじりもしていたし、病院にも自分の足ででかけていた。
だから金曜日の昼休み、卵焼きを箸で割っていたときにかかってきた祖母のかかりつけ院からの電話にも、保険証でも忘れて行って次回持ってくるようにとのリマインドかな、くらいの、経験則からの予感しかもたなかった。すぐに来てください、と祖母の容体を端末の向こうで声を抑えて伝える医師のことばの意味も、理解しているようでしていなかった。そんな日はもっと遠くで待っていると思っていたのだから。
人は徐々に弱っていくのではなかったのか。病名を告知され、ゆっくりその現実を受け入れている最中に別れが訪れるのではなかったのか。わたしたちには二日間弱しか与えられなかった。海外にいる両親はぎりぎり間に合わず、わたしは叔父と叔母とともに、祖母を看取った。こんな別れは、きいていない。
「大変だったな」
ただ粛々と通夜・葬儀を手伝った。病院に駆けつけた金曜日の半日、翌週月、火曜日と学校を休んで、水曜日、わたしは学校にいた。
久々知は自宅で行われた通夜に顔を出してくれて、ひと言、ふた言、形式的なやりとりをわたしと、お母さんと交わした。浮かない顔で帰りたがらない───本人がそう言ったわけではないが───久々知を何度か自宅へ連れて行ったことがあるから、久々知はばあちゃんと面識があった。帰って夕飯は食べるという久々知にお茶とかりんとうだけ出して、居間でふたり課題を片付けたのが、最後だったのではないだろうか。「ちゃんにこないハンサムなボーイフレンドがおるなんてなあ」とばあちゃんは目を細めたが、「久々知はジャスト・ア・フレンズ・オブ・マインだよ」「……じゃすこ?」「ちがーう! もうイオンだし!」。
通夜と葬儀と玄関前で受付し、葬儀では別れのことばを孫を代表して読んだ。明け方にスマートフォンに打ち込んだ文章は今になって思えばちょっと詩的すぎて笑える。実感がなかったばあちゃんの死も、場の空気が理解を促した。どうしたってしゃくり上がる声を必死に抑え込んだわたしの挨拶に、喪主の叔父をはじめとする親族のすすり泣く声が耳にこびりついているし、端に座っていた住職が鼻をすすり、ハンカチを目頭に押さえつける様子も目の端にとらえていた。
「大丈夫か?」
「うん、大丈夫だよ」
わたしはこうして生きている。朝起きて、制服に着替え、自転車を漕いだ。生きているから、これから、死ぬことができる。生きているのだ。だから、大丈夫かと問われれば、大丈夫だった。
久々知はわたしが休んでいたあいだのノートのコピーを机に置いて、自席に戻っていった。きれいな字がコピー用紙に几帳面にならんでいた。
監督はしばらく休むといいと言ったけれど、動いているほうが気がまぎれるということも知っていたようで、わたしが部活に出ることを止めることもなかった。
更衣室から出て、駐輪場へ向かう足がふわふわとした。お母さんは一週間ほどこちらへ残ると言い、今晩は肉じゃがをつくって待っていてくれるはずだ。お腹がすいている。だから、帰りたかった。でも、帰るのが怖かった。街灯が照らすかたいコンクリートがぬかるんだ土になっているようで、足がすくんだ。
「元気ないっすね」
「……それは、まあ」
背中に受けた声は、振り返らずともサッカー部の後輩である次屋だとわかる。
良好な関係を築いていた身近な人間を亡くしてすぐだ。元気そうにみえるならそれはわたしの演技力をほめるべきなのだが、そうはみえなくてもそこは指摘せずそっと見守っておいてほしいところだった。なぜなら、元気ではないからだ。それに、次屋だってわたしが忌引きであったことくらい知っているはずだ。
「俺にできること、ありますか?」
山奥の火葬場に着いたとき、傘をささなくても気にならないくらいの、雨が降っていた。ばあちゃんが扉の向こうへ行ってしまってから、姿をかえてまたわたしたちの前にやってくるまでの時間、わたしは煙草を吸わないのに外の喫煙所に立っていた。屋根がついていたからだった。
そうして、どれくらいか経ったとき、母はただわたしのとなりに佇んでいた。わたしの頭をなでるでもなく、抱きしめるでもなく、なぐさめのことばを言うでもなかった。ほんとうにわたしの右隣に適度な距離を保って立っていて、「そろそろ戻ろうか」と、わたしより先に歩き始めた。
母はそういう質の女で、ばあちゃんもどちらかというとそんな女で、わたしはそんな女たちによく似ている。
スカートが汚れることを気にしないわけではなかったけど、わたしは次屋の腕をつつむシャツをつかんで二の腕から手首までするするとその手を移動させながら、地面にお尻をつけた。それに合わせるように、次屋はズボンがどうなろうと知ったことのない様子でどさり、と日々生徒のローファーやタイヤが通過するコンクリートに腰をおろし、三角座りするわたしのとなりで両足を放り投げている。
「……少しだけ、こうしていてくれると助かる」
「お安い御用です」
お母さんもばあちゃんも、こうしてお父さんやじいちゃんにやさしくされた夜があったのかもしれない。
いくつかの胡乱な視線を肌に感じながら、わたしはただ次屋のとなりで膝を抱えた。